


大阪にある和食ファミレスランキング4選

和食と洋食のカロリーの比較について

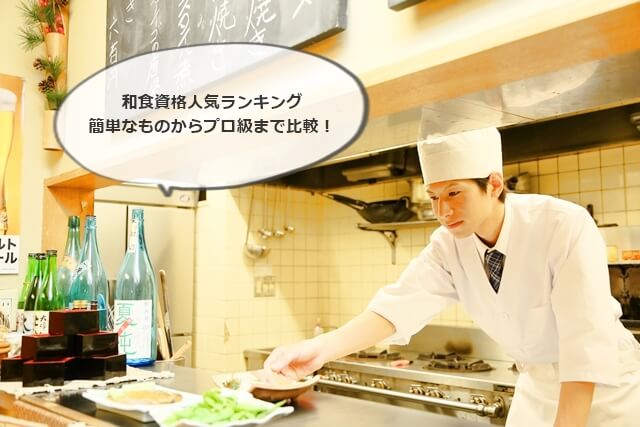
日本の伝統的な料理を指す言葉である「和食」ですが、この言葉のもつ意味は、今や単なる料理のカテゴリーとしてだけにとどまりません。
和食はユネスコ無形文化遺産にも登録され、健康作りの手段や文化としても世界中から注目されている分野です。
そのような和食に関する技術や知識を目に見える形で示してくれるのが、様々な資格です。
和食の資格には、ご家庭での食事作りのためになるものから、プロフェッショナルとしてサービスを提供するために役立つもの等、幅広い用途があります。
さらに、和食は単なる料理のカテゴリーの一つではなく、その歴史や文化も重要な要素になります。
よって、資格の中身も、調理方法、歴史、マナー、栄養など多様です。
本記事では、和食に関する資格を、役立つシーンや難易度等で分類しながら紹介します。
目次
最近では、テレビなどで男性が料理をする場面が多く見られることもあり、料理は男女関係なく、ちょっとしたブームになっています。そんな料理に関する資格は様々なものがありますが、やはり一番は基本の和食をマスターしておきたいところです。
和食の繊細な味わいと見た目の美しさは、世界的にも評価が高く、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。日本人として、和食はぜひ学んでおきたい料理だといえます。
まずは、和食の資格で人気のものを厳選しました!
和食資格のなかで人気が高い資格は、「和食ソムリエ」でした。
この資格は、食品に関する資格を多く取り扱う、日本安全食料料理協会が認定するもので確かな資格です。この資格を取得することによって、和食に欠かせない和包丁などの道具の正しい使用法や正しいだしの取り方、煮物など和食の基本的な知識・技能を身につけることができます。

資格取得後は、正しい知識や技能を使えるようになるだけでなく、お料理教室などで講師として活躍することも期待されます。この資格の保持者のなかには、料理研究家の方もおられ、基礎的な知識から専門的な知識・技能が身につく資格です。
和食をしっかりと基礎から学びたいとお考えの方から、ご自身の和食に関する知識を更に深いものにしたいという方まで、様々な方にとって有用な資格だといえるでしょう。
和食ソムリエとは、日本安全食料料理協会で和食に関する知識を持つ人材として認定されています。基本的な和食の知識、技術、技能を有していることが認められます。
受験資格は特になく、試験は2ヵ月ごとに行われています。受験料は10,000円(税込)、在宅で受験することができることも魅力的な面があります。資格取得後は、自宅やカルチャースクールなどで講師活動ができ 活躍の場が広がります。
次に、ご紹介する資格は「日本料理インストラクター」です。専門知識を教えるスキルの向上のための機関、日本インストラクター技術協会の認定資格です。
この資格を取得された方は、日本料理の基礎的な知識、懐石料理に関する知識、季節に合わせた日本料理レシピの構築が可能な知識を有すると認められます。 この資格を取得した方は、日本料理に関して確かな知識があるという認定を受けるので、日本料理のインストラクターとして活動することができます。

日本インストラクター技術協会が主催する日本料理インストラクターとは、日本料理に関する知識から、それを教える講師として認定されます。季節による料理レシピの構築や、懐石料理に関する知識、レシピの構築のスキルを証明できる資格です。
具体的な内容は、だしや日本料理に用いられる調理器具、調理技法などです。受験資格は特になく、試験は偶数月の20~25日に行われます。
受験料は10,000円(税込)、在宅で受験することができます。料理人というだけでなく、自身のスキルアップを目指したい、日本料理に関して深い知識をつけたいという方に注目されている資格です。
この「和食検定」は和食マナーなどを中心とした和食文化の知識や、それをレクチャーする技能が評価される検定試験です。
こちらの資格では、調理を学ぶというよりは、和食に関するマナーや歴史、文化について学ぶという意味合いの強い資格です。レストランや旅館などで和のサービスを行う人向けの資格といえます。

和食検定とは、一般財団法人日本ホテル教育センターが実施する民間の検定試験です。日本の食文化を正しく理解し、それを正しく伝えるための基礎知識と和の食文化を継いで普及していくために必要な専門知識、それから実務知識の理解度を測るための筆記試験です。
和食だけではなく、おもてなしの技術向上、和食を日本の文化として海外に発信できる人材の育成を目指し、より深く和について学べるため、人気を集めています。
和食検定は初級、基本、実務のレベルに分かれています。受験日は、10月と2月の年2回行われます。受験料はレベルごとに異なり、初級レベル4000円、基本レベル5000円、実務レベル8000円となっています。
資格取得後には、レストランや旅館、ホテル、観光関連のサービス業、そして調理の仕事などに既に携わっている人がさらなるスキルアップのために受験される方も多いです。
「和食マイスター」は、和食の作法、調理、食材などについて一定以上の知識があることの証明となる資格です。
日本文化の普及のための資格という趣旨のもので、和食に関することを概括的に学べる資格ですが、専門性には少し弱いという印象です。

日本野菜ソムリエ協会が主催する和食マイスターとは、世界的にも健康的であると評価されている和食の知識に関して行われている認定資格で、和食に関する知識などから日本食文化の紹介、和食の食事マナー、和食の歴史などの素晴らしさを広めるための活動を行ない、注目されている資格です。
コースが決められており、誰にでも学びやすい点も魅力的です。しっかりと和食に関する知識を身につけ、趣味や仕事で生かすこともできます。
資格を取得するには所定の講座を履修必要があります。まずは、ジュニア和食マイスター資格を取得しておく必要があり、ステップごとに資格を取得する必要がある仕組みになっています。
和食の礼儀作法、食材、調理法などの総合的な知識があることを認定する資格がこの「和食アドバイザー」です。
和食に関する知識を伝え、適切なアドバイスができる方が認定されます。こちらも実際に調理を学べるというよりは、和食を概観的に学べるというものです。

一般社団法人日本実務能力検定協会が主催する和食アドバイザー検定とは、和食の知識や技術を習得し、その魅力や素晴らしさを多くを伝えることのできる人材を育成する検定です。ユネスコ無形文化遺産に登録されたことにより、今 注目を集めた和食に関する検定です。
この資格は、和食アドバイザーとジュニア和食アドバイザーの2種類があり、ジュニア和食アドバイザーは在宅で受験が可能なことも魅力です。
試験は年に2回行われており、ジュニア和食アドバイザーの受験料は、6.320円(テキスト代・税込)、和食アドバイザーの受験料は、64.800円(税込)です。和食ブームの今こそ人気の資格となっています。
いかがでしたか。それでは、もっと詳しく各資格のことをご紹介します。紹介していない資格も載せていますので、是非ご覧くださいね!
また、和食のお店の開業を目指す方向けの記事も最後に載せていますので、開業を目指される方は必読ですよ!
和食に関する基本的な知識があることを認定する資格です。
趣味で和食について知りたいという方や、カルチャースクール等での講師活動をしたいという方を対象としています。
認定試験は2ヶ月に1度と頻繁に行われており、自宅で受験ができます。受験料も10,000円とあまり高くないので、気軽に受けやすい資格です。
また、特に指定のテキストや講座が無く、独学でも受験できます。
ですが、認定のための教室や通信講座などもありますので、興味がある方はそちらを受けてから認定試験に挑戦してもよいかもしれません。

2ヶ月に1度行われる試験期間中に、答案を作成・提出し、70%以上の評価を得ることで、認定されます。
在宅にて、指定の問題に対する解答を作成し、試験期間内に送付します。
出汁の材料や、食材に合わせた道具の使い分け、調理法といった、和食の基礎に関する知識が問われます。
〒105-0022
住所:東京都港区海岸1-2-20汐留ビルディング3階
協会名:日本安全食料料理協会
E-mail:info@asc-jp.com
インストラクターという名前の通り、日本料理について教えることができる技能を持っていることを認定する資格です。
和食の中でも、主に料亭などで食べるものを指す日本料理に関する知識に重きが置かれています。
調理法だけでは無く、懐石料理など形式に関する知識も必要になりますが、試験は2ヶ月に1回と受けるチャンスは多く、また自宅で受験できますので、チャレンジしやすい資格の1つです。

受験資格は特に無いので誰でも受けることができます。
申し込むと、試験問題と解答用紙が送られてきます。指定の期間内に解答を作成し、郵送で提出します。正答率70%で合格となります。
指定の教科書等は特にありませんが、受験対策の通信講座などがあります。
送られてきた問題に沿って解答を作成し、提出します。
日本料理の特徴である、素材の味を生かす調理法や、季節に応じたメニュー構築、また懐石料理などの本格的な日本料理の形式に関する知識等が問われます。
〒102-0084
住所:東京都千代田区二番町5-2麹町駅プラザ901
協会名:日本インストラクター技術協会
E-mail:info@jpinstructor.org
伝統的な和食の食材や文化の知識が身についていることを示す資格です。
通信講座形式になっており、学習から試験まで全てを在宅で受けることができます。
講座のセットにはテキストの他、文化やマナー、行事食について動画で学習できるDVDが付属しています。
最短2ヶ月で取得することができますので、初心者でも比較的受けやすい資格といえます。
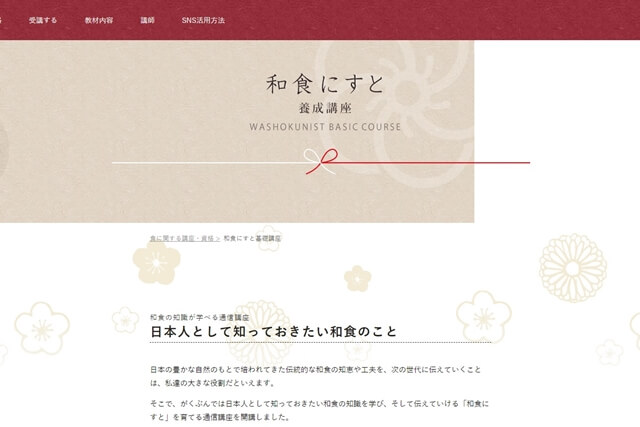
テキストやDVDによる通信講座(最短2ヶ月・標準4ヶ月)を受けた後に、課題を提出し合格する必要があります。
課題は講座のセットに同梱されています。
在宅にて、指定の問題に対する解答と、レポートを作成し、認定期間内に送付します。
和食の特徴や歴史、配膳などのマナー、日本の暦、伝統食材などの知識が問われます。
〒162-8717
住所:東京都新宿区早稲田町5-4
協会名:がくぶん
電話番号:0120-004-252
食文化としての和食の知識を持ち、それを国内外に伝えていくことができる人材の育成を目的とした資格です。
この検定は日本ホテル教育センターが管理しており、主に旅館やホテルといったサービス業における、いわゆる「おもてなし」に関する知識・技能を証明することができます。
「初級」「基本」「実務」の3つのレベルがあり、「初級」は和食に興味関心を持つ人を、「基本」は和食のプロに興味を持つ人や、プロの卵を、「実務」は実際にサービスに従事するプロや、その育成を行う立場の人を対象としています。

指定の会場で受験し、レベル毎に設定された正解率を達成することで取得することができます。
認定レベルは、初級は3段階、基本と実務は2段階にそれぞれ分かれています。
なお、実務レベルは、基本レベルの1級もしくは2級の認定を受けてから受験することができます。
それぞれのレベルに対して公式テキストが販売されています。試験問題は公式テキストから出題されますので、事前にテキストで学習する場合がほとんどでしょう。
また、試験とは別に、説明会と同時に開催される無料の対策講座もあります。
選択式で解答します。初級レベルは試験時間60分で100問、基本と実務レベルは試験時間90分で200問が出題されます。
個人受験の他に、学校や企業単位での団体受験も可能です。団体受験は5名以上から受け付けしています。
歴史や、年中行事等の季節や、箸の使い方などのマナー等の知識が試されます。また、外国人にサービスを提供する際の英語力なども必要になります。
実務レベルにおいては、接遇マナーや着物の知識、さらに経営等幅広い知識が問われます。
〒164-0003
住所:東京都中野区東中野3-15-14
協会名:一般財団法人日本ホテル教育センター
電話番号:03-3367-5663
和食の作法や歴史等、食文化としての和食についての知識を示すことができる、講座形式の資格です。
日本の伝統的な食文化である和食を大切にし、その素晴らしさを伝えたい、という人に向けた講座です。
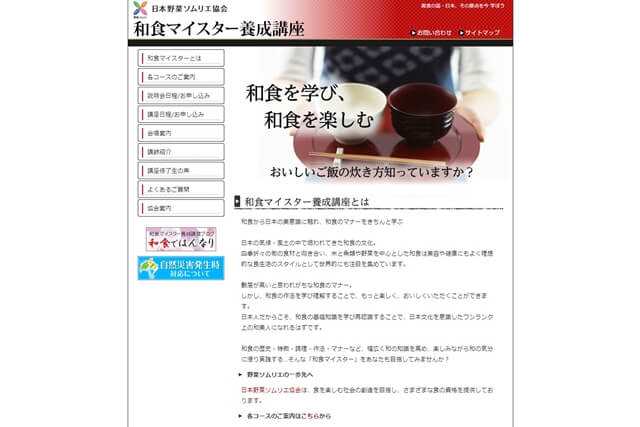
全5回の養成講座を受けた後、終了試験に合格することで取得できます。
講座を受けた後、修了試験を受験します。
修了試験を受けるためには、3回以上講義に出席していることが必要になります。
テキストや講座の内容から出題されます。
講座では歴史や器具の知識、作法やマナーの知識、主食・汁物・おかずなどの料理の知識を学びます。
〒104-0045
住所:東京都中央区築地3-11-6
協会名:日本野菜ソムリエ協会
電話番号:03-6278-8456
日本料理の専門家として、メニュー開発などから、開業やコンサルティングなどの経営面まで幅広く活躍出来るスペシャリストであることを示す資格です。
具体的には、日本料理店の経営者や、料理に関わる機器の開発事業者などを目指す人に向けた資格です。
1級から3級までがあり、3級では日本料理やマーケティングに関する知識、2級では販促に関する課題が追加され、1級ではさらに調理の実技試験が課せられます。
また、検定とは別に技術に関する通信講座があり、講座を受けていると検定料が割り引かれたり、一部試験が免除になったりします。また、講座を受けた上でそれぞれの級に合格すると、“○級BTC資格”となり、資格がグレードアップします。

それぞれの級に分けて、日本料理プロデューサーの取得方法をご説明します。
検定テキストや問題集で学習した後、在宅で筆記試験を受けます。
協会会員に登録し、検定テキストや問題集で学習した後、在宅で筆記試験と実技試験を受けます。なお、通信講座資格を取得している場合は、実技試験が免除になります。
2級を取得した後、6時間(2時間×3単位)の認定講座と実技試験を受けます。認定講座をすでに受けているが、不合格だった場合は、次回以降の試験において講座受講が免除されます。
それぞれの級に分けて、日本料理プロデューサーの試験方式をご説明します。
在宅にて、筆記試験を受けます。
在宅にて、筆記試験と、実技試験(コンセプトシート・オープンチラシの作成)を受けます。
認定講座を受けた後、実技試験(調理)を受けます。
それぞれの級に分けて、日本料理プロデューサーの試験内容をご説明します。
歴史や、調理法、マナーなど日本料理の基本的な知識と、マーケティングや開業計画などの経営に関する基本的な知識が問われます。
文化や食器等の料理に関する知識、メニュー開発や販売促進などの経営・運営に関する知識が問われます。実技試験として店舗のコンセプトシート(規模や業態、住所立地等)と、その新規開店の際のチラシの作成・提出が必要です。
認定講座受講後、実技試験を受けます。試験は、開業計画書と、実際に調理した作品の提出です。開業計画書は事前に作成した店舗のコンセプトシート(店名や業態、住所立地等)を基に作成します。調理は、3品をレシピと共に提出します。
それぞれの級に分けて、日本料理プロデューサーの取得の流れをご説明します。
〒810-0073
住所:福岡市中央区舞鶴1-1-11天神グラスビルディング9F
協会名:日本フードライセンス国際協会
電話番号:0120-941-758
和食の魅力を広く伝えることができる能力を持っていることを示す資格です。和食における調理・加工の基本や、季節の食材や郷土料理等の知識が問われます。
また、アドバイザーの育成を目的としており、食に関するコミュニケーション能力も試されます。
1級から3級までがあり、3・2級では、筆記による試験が、1級では、講座の受講に加え調理などの実技試験が課せられます。

それぞれの級に分けて、和食アドバイザーの取得方法をご説明します。
公式テキストや参考図書で学習した後、在宅で筆記試験を受けます。
2級を取得した後、3日間の実技講習に参加し、修了試験を受けます。
それぞれの級に分けて、和食アドバイザーの試験方式をご説明します。
在宅にて、選択方式で解答します。3級は、随時チャレンジできるインターネット受験も可能です。
講座受講後に、会場にて終了試験を受けます。
それぞれの級に分けて、和食アドバイザーの試験内容をご説明します。
公式テキストより出題されます。郷土料理、季節・行事にふさわしい食材や料理、調理加工技術に関する知識が問われます。
3級の内容に加え、参考図書からも出題されます。また、基本的知識を元に総合的に考える能力も試されます。
調理加工や、季節の食材などの調理に関することや、礼儀作法、更に和食の魅力を伝えるためのコミュニケーション技術等が問われます。
それぞれの級に分けて、和食アドバイザーの取得までの流れをご説明します。
〒371-0805
住所:群馬県前橋市南町2-31-1
協会名:一般社団法人日本実務能力教育協会
電話番号:027-221-1331
和食の肝である「だし」に注目した資格です。調理や商品開発などに生かせる知識を深める他、「だし」の観点から日本の郷土料理や食文化についての知識をもち、広めることの出来る人材の育成を目指しています。
また、上級では洋・中のだしについても学び、グローバルな観点からだしを知ることができます。
1級から3級までがあり、取得には各級毎に開かれる講座を受講する必要があります。
3級は、半日の講座を受けるだけで取得できますので、気軽に受けることができます。2・1級では、講座の受講に加えて、試験が課せられます。

それぞれの級に分けて、だしソムリエの取得方法をご説明します。
半日の講座を受けることで取得できます。
2日間の講座を受けた後、試験に合格することで取得できます。
それぞれの級に分けて、だしソムリエの試験方式をご説明します。
講座を受けることで自動的に取得でき、試験の受験はありません。
講座修了後に、会場にて終了試験を受けます。
各級毎に以下の内容で講座が行われ、最後に講座内容に基づいた試験が課せられます。3級は講座のみで試験はありません。
それぞれの級に分けて、だしソムリエの試験内容をご説明します。
世界のだしと料理、だしのもととなるうま味、日本の基本的なだしの種類と使われる材料について問われます。
日本人の食生活の変遷、だしから見た調理法、洋・中の料理とだしについて問われます。
それぞれの級に分けて、だしソムリエの取得までの流れをご説明します。
〒106-0047
住所:東京都港区南麻布2‐8‐11パールハイム青木501
協会名:一般社団法人だしソムリエStyle
E-mail:info@dashi.be
食生活に関してアドバイスや指導ができる知識を持っていることを示す資格です。
よりよい食生活について興味のある人や、飲食店や介護施設、教育関連施設で働く人などを対象にしています。
内容は幅広く、栄養面はもちろん、衛生や食品表示などに関する知識や、箸づかい、配膳のマナーや行事食といった和食に関する知識が求められます。
和食に特化した資格ではありませんが、食生活を豊かにする「文化」としての和食に深く関わる資格と言えます。
検定試験の他、合格のための講座も別途用意されています。現在は、3級と2級が開講されています。

指定の会場で受験し、級毎に設定された正解率を達成することで取得することができます。
指定のテキストや必須の講座等はありませんが、合格に向けた1日講座や、通信講座が開講されています。
それぞれの級に分けて、食生活アドバイザーの試験方式をご説明します。
マークシート方式の筆記試験です。
マークシート方式と記述式の筆記試験です。
食生活全般に関する知識が問われます。栄養と健康、行事食やマナー・配膳、食品表示、食中毒、マーケット、時事的な話題など、幅広い分野から出題されます。
それぞれの級に分けて、試験内容をご説明します。
主に消費者としての視点からの問題が出題されます。
主に食を提供する立場からの視点で出題されます。
〒160-0023
住所:東京都新宿区西新宿7-15-10大山ビル2F
協会名:一般社団法人FLAネットワーク協会
電話番号:0120-86-359303-3371-3593
専門学校が主催する、日常的に食する家庭料理全般に関する知識・技術をもっていることを示す検定です。
5級から1級まであり、対象が小学生から食に関するプロを目指す人まで幅広いのが特徴です。
5・4級は小中学生・基本について学び直したい大人を、3級は高校生から大学生・専門学校1年生程度を、2級以降は食品系の専門学校生や大学生程度のレベルを目安としています。
また、3級以上では、調理に関する実技試験が課せられます。

それぞれの級に分けて、家庭料理検定の取得方法をご説明します。
指定の会場にて筆記試験を受け、設定された正解率に達成することで取得できます。
指定の会場にて筆記試験と包丁技術や調理技術を試される実技試験を受け、合格することで取得できます。
筆記試験の合格者のみが、実技試験を受けることができます。
それぞれの級に分けて、家庭料理検定の試験内容をご説明します。
筆記試験です。内容は、簡単な食文化や栄養、調味料・調理法などの知識について問われます。
筆記:季節の料理などの食文化や1日に必要な栄養素、基本的な調理法と衛生などに関する知識
実技:基本的な包丁技術
筆記:季節の料理や行事食などの食文化、生活習慣病と食事の関係、食品の特徴に応じた調理法、アレルギーや衛生に関する知識
実技は下記のとおりです。
筆記:マナーや配膳、旬の食材などの食文化、ライフステージに応じた献立作り、食品の特徴に応じた調理法、食品表示などを含めた衛生に関する知識
実技は下記のとおりです。
筆記:歴史や形式などの食文化、シーンや対象者に応じた食事計画、和・洋・中の調理法、外食を含めた栄養、もてなしの家庭料理などに関する知識
実技は、食事シーンや食べる人の年齢・性別等を想定した1食分の献立考案と調理実技になります。
それぞれの級に分けて、家庭料理検定の取得までの流れをご説明します。
〒170-8481
住所:東京都豊島区駒込3-24-3
協会名:学校法人香川栄養学園家庭料理技能検定事務局
電話番号:03-3917-8230
和食は生活に深く根付いた身近なものである一方、長い歴史と伝統のもとに成り立っているものであり、マナーやしきたりなどがつきものです。和食のプロともなれば、調理だけでは無く、文化としての面も学ぶことが必要になります。
また、調理においては、高度な包丁さばきなどの技術や、盛りつけや器との調和と言ったセンスが求められます。

資格が無くても働くことはできますが、専門学校や食品系大学などで調理師免許を取得したり、専門的知識を学んだりしている方が有利になります。また仕事内容にそった民間資格を持っていると、知識があることをアピールすることができます。

美味しい料理を提供するためのノウハウはもちろん、飲食店関連の法律や経営に関する知識が必要になります。さらに店舗の具体的なイメージ、コンセプトを作った上で、資金集めや、実際の設備の導入・スタッフ採用などを行います。

様々な和食の資格を紹介しました。自分の仕事にどのような和食の資格が必要か、どのような和食の資格を持っていた方が有利かをよく調べた上で、どの資格を取得するかを選んだ方がよいでしょう。
また、無料の資料請求を受け付けているスクールも数多くあります。必要に応じて、資料請求を行って、しっかりと比較すると希望に合った資格が見つかりやすいでしょう。
和食の資格は、通信教育で取得できる資格も多くあります。和食の通信講座の種類を紹介していますので、是非ご覧くださいね。